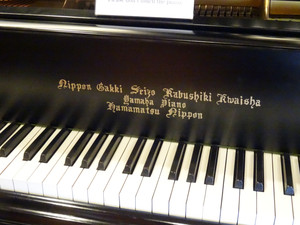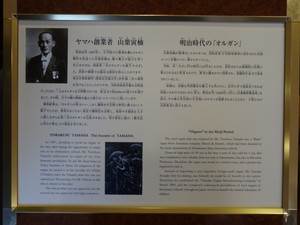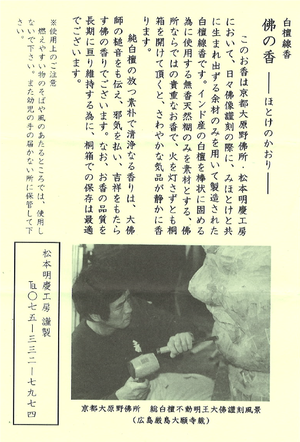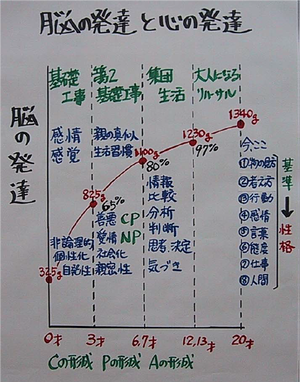以下、時間が無ければ読む必要はない。文章読本の記録として掲載。
6.1.2 『文章読本』私見
現在の文章読本の抱える問題点
⑴本の読者対象が明確でなく,かつ小説用,エッセイ,ビジネス・技術論文用の用途が明快に指定されたのは少ない。
題名から判断すると日本では暗黙の内に下記のように分類される。
文章読本 小説家が記述 小説,随筆用
文章作法 ジャーナリスト・評論家 随筆,新聞記事用
・・表現法 大学教授・評論家 論文,レポート,一般文書用
・・作り方 大学教授・評論家 論文,レポート,一般文書用
・・書き方 大学教授・評論家 論文,レポート,一般文書用
・・技術 大学教授・評論家 論文,レポート,一般文書用
・・上達法 大学教授・評論家 一般文書
・・入門 エッセイスト・評論家 手紙,投稿等
⑵文章読本の文体自体,構成自体が「美しく」ないのが多い。文章読本である以上、普通の書とは一線を期すべく,格調高い文体で書くべきか,もしくは徹底してマニュアルらしく記述すべきだと私は思う。
⑶対象読者のレベルを明確にしていないので,読んでいて馬鹿にされた気にさせられる内容が目につく。
曰く「原稿用紙は・・・を使いましょう」
「校正者に読めるような丁寧な字で書きましょう」
「締切期限は守りましょう」
「下書きをしましょう」等々
⑷漠然とした指示,指針のため,では具体的にどう書けば良いかと質問したくなる内容が多い。
⑸エッセイなのか,マニュアルなのか曖昧な書が多い。
⑹辞書を見れば記載されている漢字の用法,読み方等の内容を数頁に渡って掲載してある書が目立つ。これではページ稼ぎとしか思えない。
⑺大学教授,文章塾の講師の書で自分こそ文章読本を書く資格ありと豪語している書が目につく。そういった書に限って,上記の不具合を持つ例が多い。
以下に私が目を通した『文章読本』と文章に関する書を,
⑴小説家の本家としての『文章読本』
⑵大学教授,評論家,ジャーリスト等のビジネス文用『文章読本』
⑶文学,エッセイ,随筆用『文章読本』,それに関する書物
の3つに分類して,感想を記述する。
6.1.3 小説家の著した『文章読本』(出版年順)
谷崎潤一郎著『文章読本』 中央公論社 1934(昭和9年)
文章読本として,バイブル的存在の名著であるとされている。しかしこの名著の声はあくまでも文学作品用としての文章読本である。この書では日本語の品格と余韻、含蓄の重要性を説いている。また文章の見た目の美しさ、リズムの重要性を説いている。曰く「言葉というものは出来るだけ省略して使いなさい」、「大事なのは余韻,余情だ」、「言いたいことが十あったら言葉で表すのは五つに留め,残りは余韻として残す。そうすれば五つの余韻が何倍にもひろがっていく」
この余韻は清少納言著『枕草紙』の「言葉は不具なるこそよけれ」や吉田兼好著『徒然草』の「よくわきまえたる道には,必ず口重く問わぬ限りは言わぬこそいみじけれ。」(79段)などの言葉に対する過少評価を旨とする日本人の伝統からきていると私は思う。全てを言い尽くしてしまう言葉より余韻,余情が残っていたほうが良いとする言語観を谷崎氏は上の言葉で著したと推定される。
この書は文学、エッセイ等の記述のためには読むべき示唆は多いが,論理性の必要なビジネス文・技術論文用には向かない。谷崎氏がいう含蓄の重要性はビジネス文・技術論文では最も避けねばならない事項である。
またこの書の内容は,昭和9年に出版された時代背景を考慮すると興味深い。この時代,日本文学や思想が西洋主義から伝統主義,日本主義に転換する時代背景が文章読本の形で表現されている。谷崎自身も,従来の欧米調の明晰な文から『細雪』に代表される情緒を主体とする文体へ変化している。この変化を促した事情は下記の昭和9年前後の社会情勢を見れば納得がいく。
昭和3年 関東軍,張作林を爆殺す
昭和6年 柳条溝事件(満州事変)
昭和7年 515事件,警察庁に特高警察部,各県に特高警察課設置
昭和8年 河上肇検挙,小林多喜二虐殺さる,国際連盟脱退
昭和9年 文部省に思想局設置
昭和10年 天皇機関説事件(美濃部達吉『憲法撮要』発売禁止)
この時代,言いたいことがハッキリ言えない時代になってきた背景を考えると,谷崎氏の言う余韻,含蓄の持つ別の意味合いが明確になる。この事情を念頭にこの文章読本を読むことが必要と考える。
三島由紀夫著「文章読本」 中央公論社 1959(S34)
この書での主題は文の品格と格調であり,あくまでも文学作品用と理解したい。小説,長短編小説,戯曲,評論文の記述の違い,人物描写,心理描写等で読むべき点は多い。
「(文学作品として)あるものを描写する場合は,主語が単調にならない様に変化させて記述せよ」といった科学・工業英語の発想とは正反対の記述がある例からも文学はビジネス文とは違うことが認識される。また,文学として形容詞の使い方の重要性も説いている。形容詞の役割が,文学用とビジネス文を峻別する。また文章の味わいと言った表現でその質を感性として重要視している。
三島氏は「小説は歩行の文章,戯曲は舞踏の文章」と書いている。小説が勝手きままな歩行と言うなら,私は「ビジネス文は整然たる行進の文章」としての形式が必要と考える。
丸谷才一著 『日本語のために』 新潮社 1974
丸谷才一著 『文章読本』 中央公論社 1977
丸谷才一対談集『日本語そして言葉』 集英社 1984
谷崎氏の文章読本からはじまって,文壇の各氏の文章読本を比較、批評しているのが興味を持たれる。ここに氏の考えが出ている。名文の基準が過去何処にあったかが記述されていて面白い。氏の研究熱意が伝わる書である。ただし,これは文章を書くためのマニュアルではない。
丸谷才一編 『恋文から論文まで』 福武書店 1987
この書も文学としての文章論である。井上ひさし氏はこの書を「考える文と感じる文の実例」として大きく評価している。一読の価値はある。
しかし,小説家,文学者,評論家の23人が文章についての独自の論陣(一人平均9頁)を張った内容を一冊にまとめたため,体系的なまとまりがないのが残念である。
井上ひさし著『自家製文章読本』 新潮社 1984
川端康成著『新文章読本』
伊藤整著 『文章読本』
上記二冊はゴーストライタによって記述されたとの噂があるので批評は避ける。川端氏の文章読本は、雑誌に連載した各章ごとを編集しているせいかまとまりがない。またその内容は私には明確には理解しがたい。
6.1.4 大学教授,評論家,ジャーナリストが著した文章読本
立花隆著 『知のソフトウェア』 講談社現代新書
著者は「田中角栄研究」で有名。氏の文章を削る技法のノウハウには一読の価値がある。
板坂元 編 『ことばの技術』 フォー・ユー 1990
説得の技法,言葉の持つニュアンス等を記述。
板坂元 著 『考える技術・書く技術』 講談社現代新書 1973
板坂元 著 『続・考える技術・書く技術』 講談社現代新書 1977
板坂元 著 『日本語を外から見れば』 創拓社 1989
板坂元 著 『異文化摩擦の根っこ』 スリーエーネットワーク
板坂元 著 『キラリと光る文章技術』 KKベストセラーズ 1992
外山滋比古著『思ったことを思い通りに書く技術』青春出版社
一読の価値あり。
外山滋比古著『英語の発想・日本語の発想』 NHKBOOKS 1992
NHKラジオテキスト「英会話」紙上に連載されたのを編集した本。二つの言語の表現の差,その背景,理論的説明等をまとめた内容は,視点が的を射ていて,読ませる。文章読本ではない。
外山滋比古著『山茶花はなぜサザンカか』 朝日新聞社 1990
外山滋比古著『ことばの作法』 三笠書房 1987
ハーバート大学教授の板坂元氏,お茶の水女子大学名誉教授の外山滋比古氏の書は日本語に関する良質の知識が散りばめられていて,知的好奇心が堪能させられる。どれも一読の価値がある。
本多勝一著『日本語の作文技術』 朝日新聞社 1976
ジャーナリストとしての文章論で、ビジネスマン,技術者に参考になる点が多い。ただし氏の偏向した考え方は問題。
以下出版年順で記載
清水幾太郎著『論文の書き方』 岩波新書 1959
技術系の文章読本には参考資料として必ずといっていいくらい,引用される有名な論文用の文章読本。名著とされている。しかし,50数年たった現代の目からみると,書の構成,各章の構成,文章の構成,文のスピード感等,首をかしげたくなる箇所が目につく。時代とともに文章の価値観,文章作成仕様も進歩するのだから,本書を参考資料の筆頭に挙げてあるような文章読本はパスが無難である。
金田一晴彦著『日本人の言語表現』 講談社現代新書 1975
日本語の構成を,歴史的,社会的な背景から解説した。一読の価値あり。
八杉龍一著 『論文・レポートの書き方』 明治書院 1971
市原A・エリザベス 著 『ライフ・サイエンス ニオケル英語論文の書き方』共立出版社
宮川松男著 『技術者のための文章作法』 日刊工業新聞社
佐藤孝一著 『博士・修士・卒業論文の書き方』 同文館 1973
とみ田軍二著 新版『科学論文の纏め方と書き方』朝倉書店 1975
尾川正二著 『原稿の書き方』 講談社現代新書 1976
中島重旗著『技術レポートの書き方』 朝倉書店 1977
イラストの書き方にページを割いている。
森本哲郎著 『「私」のいる文章』 ダイヤモンド社 1979
ジャーナリストとしての文章論を展開している。一読の価値がある。
今井盛章著『文章起案の技術』 学陽選書 1980
川上久 著 『知的表現の方法』 産業能率大学出版部 1978 書名と出版社名に期待して読んだが期待はずれ。氏は裁判官。組織としての文章の書き方を記述している。少し冗長な内容だが,参考になる点は多い。
橋本峰雄著 『論争のための文章術』 潮出版社 1980
題名はすばらしいが,「起承転結」論はいただけない。有名な小説用の文章読本の解説は明快に記述されている。しかし,書の1/3をも「自由作文」と称して題名とは関係ないエッセイを載せているのはいかがなものか。
桑原武夫著 『文章作法』 潮出版社 1980
文芸、ジャナーリスト用文章読本。内容は並以上のことを言っているが、出版が古いせいか構成、文体にスピード感がないのが残念。
木下是雄著 『理科系の作文技術』 中公新書 1981
林茂樹監修 『論文はこう書けばいい』 西東社 1981
金田一晴彦著『日本語セミナー1』 筑摩書房 1982
井口茂著『法律を学ぶ人の文章心得12章』 法学書院 1982
法学関係の文が分かりにくいのは有名である。題名から受けるイメージで期待して読んだが,文学作品向けと勘違いしそうな構成でがっかりした。
広中俊雄・五十嵐清編『法律論文の考え方・書き方』有斐閣選書R 1983
法律関係の書は難しくて,読みにくいのが定説だが,法律論文用の文章読本までが同じく読みにくいとは思わなかった。各大学の教授が14名で分担執筆している。法律の小論文の書き方で起承転結の論法が出でくるとは意外であった。
この書では,法律論文を書くための4条件を
⑴ 明確な問題意識
⑵ 言葉・文章に対する鋭敏な感覚
⑶ 事実認識における客観的な姿勢
⑷ 解釈論のもつ実践的性格の自覚
で取り上げ,解説している。私は,法律論文こそ明確な論理性・論理展開が最重要と考えていたが,上記4条件からみて法学者は技術屋とは視点が大きく異なることを認識した。
松本道弘 著『英語はロジックに強くなる』 講談社 1983
鈴木孝夫著 『武器としてのことば』 新潮選書 1985
市毛勝雄著 『間違いだらけの文章作法』 明治図書 1986
╶─╴若い教師のための論文入門╶─
文章に論理性が必要だとの点で論じている。著者は「起承転結」でなく「起承束結」で論理展開を主張している。新聞コラムに論理性を求めるのは無駄との意見には賛成だ。
山口喬著 『エンジニアの文章読本』 培風館 1988
理工系学生向け文章読本。
野口靖夫編著『書く技術表現する方法』 日本実業出版社 1988
取り上げた視点,まとめ方はユニークで工夫の跡がわかるが、5人で執筆しているせいかまとまりがない。文章読本らしい体裁で,本の半分を対談文で埋めているのもいただけない。本のネーミイグだけは素晴らしい。
大隈秀夫著『文章実践塾』 ぎょうせい 1989
エッセイ,新聞記事,小説用の文章の書き方としての文章技術なら許せる。
木下是雄著『レポートの組み立て方』 筑摩書房 1990
人文・社会科学系の学生向けの文章読本。
結論を最後に述べる「逆茂木型の文」論は,分かりやすい。
堺屋太一他 『マニュアルはなぜわかりにくいのか』毎日新聞社 1991
小川明著『表現の達人 説得の達人』 TBSブリカニカ 1991
冒頭で「あなた」といわれると,親近感より先に馬鹿にされた気がして、その先を読む気がなくなる。「あなた」の使い方の難しさが理解できる逆説的な本である。題名をその点で意味深長である。
二木紘三著 『文章上手になるチェックリスト』 日本実業出版社 1991
町田輝史著『技術レポート上達法』 大河出版 1992
「京都三条糸屋の娘・・・」で起承転結を絶賛している。
文中,話し言葉も目につくが,学生のレポート用としてみれば許せる。
高田城著『就職論文の書き方攻め方』 二期出版 1992
就職試験のための泥縄式のコツを伝授されるより,文章記述の基本を述べるのが大事だと思う。文中で「あなた」と書くのは宗教書と低学年向きの書が多いのを知るべきだ。
阪倉篤義著 『日本語の流れ』 岩波書店 1993
Roy W.Poe 編 "THE McGAW-HILL HANDBOOK OF BUSINESS LETTERS"ジャバンタイムズ マグロウヒル版英文ビジネスレターの書き方。
八幡ひろし著『プレゼンテーション技術』 日本生産性本部
渡部昇一著 『日本語のこころ』 講談社現代新書
秋沢公二著 『アメリカ人の英語』 丸善ライブラリー
品川嘉也著 『思考のメカニズム』 PHP研究所
金田一晴彦著『日本語』 岩波新書
大出あきら 『日本語と論理』 講談社現代新書
小村宏著 『外語と内語』考え方の技術 実用新書
文章ばかりでは分かりにくい。最初にまとめを記述するとわかりやすいのに。
時事教育研究会編『論文・レポートの書き方と作文技法』画文堂
段落の思想なし。起承転結等の主張している。
三島浩著 『技術者・学生のためのテクニカル・ライテング』 F.SCHOT HWEL,野田晴彦著『科学者のための英語教室』
佐々克明著 『報告書・レポートのまとめ方』 三笠書房
6.1.5 文学、エッセイ、随筆等の文章に関する著書(出版年順)
大石初太郎著『文章批判』 筑摩書房 1980
文学用。文字通り,文体の解説であって文章読本ではない。
多田道太郎著『文章術』 潮出版社 1981
手紙,小説,コラム用の文章読本。例示文章も小説,コラム,手紙,新聞記事が主体となっている。氏は良い文章の条件を①わかりやすい②面白い③間違いがすくない,で規定している。私はビジネス文とは視点が違うことを認識した。付録で「私の文章作法」として小説家,文学者,大学教授,ジャーナリストの10人が各2ページほどに意見を集約して記述しているが,このページ数では言いたいことも言えないせいか,内容が漠然としている。載せない方が良いくらいで,これでは付録ではなくオマケであると言いたい。
日本語シンポジウム『美しい日本語』 小学館 1982
昭和57年の日本語シンポジウムでの外山滋比古,稲垣吉彦,青木雨彦,芳賀綏,樺島忠夫の5人の講演と,討議をまとめた書。各々の素晴らしい講演も多人数分の講演を本としてまとめると美しくなくなる事例としては面白い。シンポシウムの記録としての価値はある。
森本哲郎著 『日本語 表と裏』 新潮社 1985
文学作品用の文字に関するエッセイとしては興味深い。
向井敏著 『文章読本』 文芸春秋社 1988
起承転結をベースにした文学、エッセイ等のための文章読本。序章の「名文の条件」において,何が名文の条件なのかを理解するのには心して「精読」をする必要がある。
井上敏夫著 『エッセー・随筆の本格的な書き方』大阪書籍 1988
大隈秀夫著『文章実践塾』 ぎょうせい 1989
エッセイ,新聞記事,小説用の文章の書き方なら許せるが。
佐藤正忠著 『文章は,心で書けばいい。』 経済界 1990
文章読本のエッセイとしてなら。
中村明著 『文章をみがく』 日本放送出版協会1991
文学作品用・・・。題名だけは素晴らしい。
森本哲郎著 『日本語根掘り葉掘り』 新潮社 1991
日本語独自の表現を通して,日本人の論理構成,ホンネ等を浮き彫りにしたエッセイ。「は」と「が」を「説明」,「叙述」の手法で定義した論法は一読の価値あり。前著『日本語 表と裏』の姉妹版。
岩淵悦太郎著『悪文」第三版 日本評論社
秋澤公次著『英語の発想法 日本語の発想法』 ごま書房 1992
─アメリカ人の考え方を知るための33のキーワード─
コミュニケーションを成立するためには、その国民性まで理解しないと、英語の直訳や日本人が認識している意味での訳では、会話が成立しないこと。それによって貿易摩擦にまで発展する恐れを秘めていることが解説されていて、興味深く読みごたえがある。学校英語とコミュニケーション英語の違いが認識できる。
久志能幾研究所 小田泰仙 HP: https://yukioodaii.wixsite.com/mysite
著作権の関係で無断引用、無断転載を禁止します。