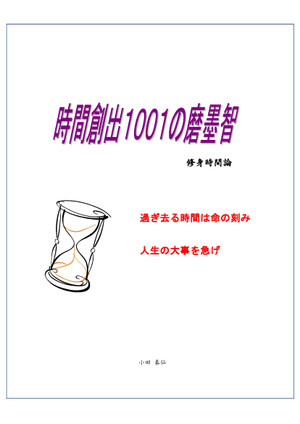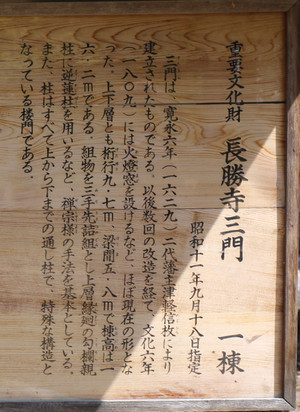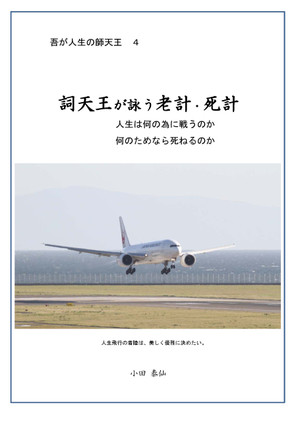上達の秘訣は、耳4、目3、手3分
2017年7月19日、馬場恵峰師のかな書道の「いろは教室」の聴講をした。そこで書道の上手になる秘訣を教わった。良く考えると、これは書道だけでなく、芸事を始め仕事や人生での全てに当てはまることに気が付いた。
耳4分
書道上達の秘訣は、「耳4、目3、手3分」であるという。目でお手本をみて、実際の手を動かして練習をする。しかしそれだけでは上達しない。耳の4分が大事である。耳とは師の教え、人の批判である。それがあって自分が成長できる。いくらお手本をみて人以上に練習をしても、師の教えがないと我流になり成長が止まってしまう。
並みの学者は、耳3、目3、手3分である。学者は最後の一分の詰めが足りない。学者は自己独善で人の言葉に耳を貸さない。だから理論倒れの経営をする。学者が大成功して大金持ちになったという話を聞いたことがない。自分のやったことを師が、他人が、第三者の目で批判してくれて、初めて己の問題点に気が付く。自分では自分の背中は見えない。自分の最大に理解者は、批評家である。
目3分
考えて書かないから、いつまでたっても上達しない。お手本ばかり見て練習しても上達しない。実践では時代も世相も変わりそれに合った自分の字を考えて書かないと、お手本以上にはならない。頭で覚えて書かないと、自分の字にならない。いくら経営の教科書通り、先代の経営の通り、師匠の経営通りにやっても、時代も世相も変わっているので、それに合った経営をしないと、うまくいくはずがない。
手3分
いくら練習を積んでも、間違った方法で練習をしても間違ったままのレベルにしか達しない。やればやるほど、そのやり方が固定されてしまう。やればやるほど唯我独尊に陥る。
時間を盗め
時間を盗み惜しみて手本の字を自分のものにせよ。経営の教科書の内容を自分のものとせよ。
継続が力
続けていれば、いつかは好きになり、自然と時間も生まれて来る。
逃げの心
私は字が苦手、練習する気になれない、は逃げの人生である。跡取りで親から二代目の社長として経営を任されても、経営は苦手、経営の勉強をする気になれないのでは、逃げの経営で倒産間違いなし。
目にみえないものに籠る魂
目に見えないもの目を向ける人が成功する。だから目の付け所という。馬場恵峰師は身銭をきって原田観峰師の書を多く購入した。これほど多く原田観峰師の書を所蔵しておられる方はいない。観峰師の書を見ていると、観峰師の魂が自分に乗り移ってくるのを感じるという。その霊魂が恵峰師を指導されたという。
天国暮らしの大学教授
その昔、年間12回、年間50万円の講習料で経営セミナーに参加したことがある。その経営セミナーは講師が2名であった。一人は大学教授である。知人の社長の数名は、その大学教授の欠点をすぐ見抜き、その講義時間の時は研修会場を抜け出しタクシーで昼間から飲み屋に行って飲んでウダを巻いていた。その講義が終わり夜の懇親会の時間になると帰ってきた。思えば、その大学教授の講義内容は、簡単な話を難しく表現していて、私もよくわからなかった。ある社長が「先生が称賛されるその偉人のお話はよくわかるのですが、それでそれを我々の経営のどう役立てればよいのでしょうか?」と質問をしたが、その教授は答えられなかった。その講師は講義時間の終了時間を「必ず」守らなった。経営者にとって時間は命である。たった2時間の自分の講義時間の経営もできずに、中小企業の社長たちに講義をするのがおこがましい。企業存亡の修羅場で生きている社長たちと違って、大学は腑抜けの天国である。この種の大学教授とは唯我独尊で、耳を持たない仏さまである。逆縁の佛様で、反面教師の役を務める。
2017-07-21
久志能幾研究所 小田泰仙 HP: https://yukioodaii.wixsite.com/mysite
著作権の関係で無断引用、無断転載を禁止します。