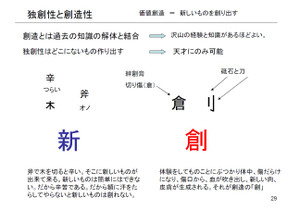上記は私が前職の時、よく周りの人の言っていたジョークです。
“Who were you? ”ではなく「不和 are you?」なのです。
「こんなにまで遅くまで会社にいて、貴方の家庭は家庭不和ですか?」
「家庭を省みず、自分の体を無理させてまで働くあなたは誰?」
「あなたは何のために働いているの?」
この意味を直ぐに理解できる人は頭がいい、もしくは後ろめたいので、すぐ真意を理解してくれる。家庭不和の状態では、家族の幸せの時間は創出できないのだ。遅くまで会社で働いているのは、時間の使い方が下手なだけだ。家族を思う気持ちが少ないだけだ。仕事も家庭も両方大事なのだ。両立させてこそ、初めて時間創出がマスターできたと言える。
運命の流れ
遠戚の叔母の子息が常務に昇進したのだが、その子息に大腸ポリープが見つかった。町医者では対応できないほど大きさの為、日赤病院で削除手術を受けた。その組織を調べたら大腸がんと診断された。それを聞いて、健康に関する私がまとめた資料を叔母に送った。私が8年ほど前に大腸ポリープで手術をした折、大腸ガンになる恐怖から、その病後の対策で、各種の本を読み漁り、それの要点をまとめた資料である。それに沿って健康管理を行って、現在は大腸ポリープに関しては健康である。その資料を叔母に郵送して、息子さんに渡して欲しいと託した。1週間ほどして、その感想を聞いたら、まだその資料を息子さんに渡していないという。今、息子は常務に昇進したばかりで忙しく、それどころではないので、渡せなかったという。命にかかわることなので、急いで送ったのに、この有様で、息子にしてその親ありである。人生の優先順位を間違えている。なんのために働いているのか、それを教えるのが親の勤めである。命を犠牲にしてまで働いて、どうするのかである。運命の糸の縺れ、他人には強制もできず、如何とも致し方ないことを悟った。病気になるのは、病気になるような躾と環境で育ったためである。親と嫁が、子息の運命の流れを変えるべき責務があると思うのだが……。私の家のお墓を改建したとき、お墓の開眼法要でその子息にも声をかけたが、出席はなかった。その時に会っていれば、面識ができたので、連絡もつくのだが、それが叶わない。運命はご先祖様が握っていることを悟った次第である。
健康になる要点
下記は自分が大腸がんになる恐怖心から、健康に関する図書を読み漁りまとめた資料の要約である。その詳細は、健康関係の図書一覧で参照ください。
- 水を1日に1リットルを飲む。
- 体を冷やさない。お風呂に毎日、10分間入る。
- 睡眠を十分にとる。部屋を真っ暗にして眠る。
- 食べるより出すことが大事。
- ファーストフードを食べない。
- 洋風の食事から、和風の食事に。
- 乳製品、肉類を少なく。
下記の健康関係図書一覧は、知人に送付した書き抜きの資料です。各資料A4で3~10頁ほど。著作権の関係で、ブログでは公開できませんが、興味があれば個別で相談に乗ります。メールで連絡ください。
健康関係の図書一覧
1.『メイ牛山のもっと長寿の食卓』メイ牛山著
情報センター出版局 2002年 1400円
【要旨】メイ牛山91歳8か月。現役の美容家が実践する、「イキイキ・楽しく・美しく長生きする」秘訣集。今日食べたモノが、明日のきれい・元気の素になる。長寿の食卓を実践する生活レシピを満載。食事の大事さが、91歳の現役という事実で実証される。生きるとは、食べること。今の体は、過去の食生活の結果です。(2010/03/29 小田)
2.『酵素で腸年齢が若くなる!』鶴見隆史著 2008年 青春出版社 1400円
【要旨】全身のリンパ組織の80%が集中する腸を、若返らせるのは酵素である。人間の体の免疫システムの要は腸内環境で、腸内環境が悪化すれば、老化がはじまり、健康を損ねる原因になる。その腸内環境を左右するのが、「酵素」で、酵素を毎日の食事で多く摂り、体内酵素をムダづかいしない生活姿勢が、いつまでも若くて元気に生きられるポイントである。酵素と腸は密接な関係にある。酵素食のレシピとファスティングによって、若返りと健康を作る。(2010/2/7 小田)
3.『病気にならない生き方1~3』 新谷弘実著 サンマーク出版
2010/01/10 小田
4.『10歳若返る心身活性法』樋口芳朗著 徳間書店 1983年 680円
【まえがき】自分にあったものを、断固継続せよ! 健康法についての情報は世にあふれています。ここで、骨身に徹して自分に言い聞かせなければならないのは、本当に大事なことは、情報を集めたり、ちょっぴりやってみるなどということではなく、洪水のような情報の中から、長続きしそうで、自分にあったものを選択し、一たん決めたら断固してある期間継続することなのです。この本では、自分がやってみて本当に確かめたもの、とくに還暦の身で、毎日実行している健康法を主として述べました。極端に各論的ですが、健康法などというものは具体的でなければ無意味であると割り切りました。(2010/07/04 小田)
5.『なぜ「粗食」が体にいいのか』帯津良一・幕内秀夫著
三笠書房 2004年 ¥560 2010/06/23 小田
6.『温泉に入ると病気にならない』松田忠徳著 PHP選書 2010年 760円
【要旨】なぜ日本人は昔から温泉が好きなのか?―近年、予防医学の立場から、病気にならないために体温を上げろと指摘する声が高まっている。では、塩素づけの水道水を沸かした家庭の風呂やシャワーで事は足りるのか。それよりも、還元力のある“生きたお湯”につかったほうが安全。体も温まりやすく冷めにくい。日本人にとって温泉は、くつろぎの場であるとともに、免疫力を高めるもっとも身近な健康管理の場だったのだ。病院に行かなくてもいい健康な心身はホンモノの温泉で十分。その活用術を温泉教授が伝授。(e-hon HPより)(2010/5/3 小田)
7.『体温を上げると健康になる』齋藤真嗣著 サンマーク出版 2009年1400円
【要旨】「体温が1度下がると免疫力は30%低下する」と著者は警鐘を鳴らす。米国・EU・日本で認定されたアンチエイジングの専門医が教える体温アップ健康法。最近、平熱が36度以下という、いわゆる低体温の人が増えている。その影響で様々な病気が発生している。その対策として、1日1回、体温を1度上げることを推奨し、体温を恒常的に上げていくことで健康な体を手に入れることができる「体温アップ健康法」を提唱している。「病気の人は健康に、体調のすぐれない人は元気に、健康な人はより美しくなる」と。(2010/03/06 小田)
8.『腸の健康革命』 新谷弘実著 日本医療企画 (2005年) 1524
【要旨】胃腸内視鏡の第一人者が、「出すことは食べることよりもっと大事である」ことを説く。腸内に老廃物、毒素、異常発酵物をため込んだり、硫化水素、活性酸素等の有毒物質を発生させないためには、食べたものを12~24時間以内に出してしまうのが理想です。(2010/02/14 小田)
9.『病気にならない人は知っている』ケビィン・ドルドー著 幻冬舎2006年1,470円
【要旨】ハンバーガーを食べるな!日焼け止めは塗るな!水道水は飲むな!歯磨き粉は使うな!牛乳は飲むな!電子レンジは使うな!風邪薬・抗生物質をのむな!ダイエット食品を食べるな!ひとつやめれば体調がよくなり、全部やめれば長寿になる。(2010/06/12 小田)
【おすすめコメント】添加物まみれの食品や土壌汚染が、私たちの体を蝕む。医学界や製薬業界、食品業界が明かさない、健康に生きるためにしてはいけないことを解説した全米900万部のベストセラー日本上陸。(e-hon HP)
10.石原結實著
①『体を温めると病気は必ず治る』三笠書房 2003
②『おなかのすく人はなぜ病気にならないのか』プレジデント社 2006
③『病気は自分で見つけ自分で治す!』KKベストセラーズ 2006
④『老化は体の乾燥が原因だった!』三笠書房」 2007
⑤『50歳からの病気にならない食べ方・生き方』海竜社 2009
⑥『病気にならない生活のすすめ』渡部昇一・石原結實著 PHP文庫 2006
【要旨】病気は、体の低体温化、食べ過ぎ、運動不足、によって起こる。
低体温化を防ぐため身体を温めることが大事です。身体の中心のお腹を温めることが大事で、腹巻はその手段として最高。入浴は体温を上げる大きな手段。また発熱作用は自然治癒の手段である。食べるより出すほうが大事である。動物は病気になると食べない。断食は排せつ機能を高める手段としてメスのいらない手術とも言われる。運動は基礎代謝力を上げ、身体を温める。(2010/04/11 小田)
『時間創出1001の磨墨智』より
2017-08-10
久志能幾研究所 小田泰仙 HP: https://yukioodaii.wixsite.com/mysite
メール:yukio.oda.ii@go4.enjoy.ne.jp
著作権の関係で無断引用、無断転載を禁止します。